はうき持て転がる落葉追ひにけり 斎藤 摂子
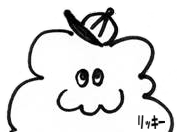
集めても風で転がってゆく落葉をあわてて追いかけている場面ですね。本人は少し困った様子ですが道行く人は「あらら大変」と笑顔で通り過ぎていきます。〈はうき持て〉が楽しい一句になりました。(谷野由紀子)
背を向けて夫は百ます秋ともし 三原 満江
〈百ます〉、ネットで引いてみました。大人では集中力・思考力・脳の活性化などに効果があるとか……。日に何回も何をするのか忘れたり、買い忘れたりしていますので私も挑戦してみたいと思いました。〈背を向けて〉が微笑ましく仲の良いご夫婦像が窺えます。(浅川加代子)
阿弥陀もて小僧役引く秋の暮 河原 まき
阿弥陀くじで役を決めているご様子。小僧が出てくるお芝居は、なんだろう。「弁天小僧」「鼠小僧」か、それともアニメの登場人物?阿弥陀で決めるから自主的なお芝居だろうな、大人かな、子どもが演じるのかな…とか色々と想像しました。こちらまでわくわくして結果を知りたくなりました。選後に作者名が分かり狂言の演目かなと……。(浅川加代子)
なけなしの髪を木枯吹き立たす 伊藤たいら
思わずにやりとしてしまいました。なけなしのお金でもなく髪の毛!作者の髪に対する思いをあれこれ想像してしまいました。無慈悲な〈木枯〉への恨み節にもとれるし、まだ吹き立つほど残っているぞと強がりにも聞こえます。いや、髪の毛を句のねたにできるほどだから拘りは捨てきっておられるとも受け取れます。初心者の私にとってわずか十七文字の俳句の奥深さと「楽しい俳句 見ぃつけた!」気分です。(溝田 又男)
アンカーはビデオ判定秋高し 小林伊久子
スポーツの秋、陸上競技の中でも花形の四百メートルリレーは、スタート前のウォーミングアップから緊張感が伝わり、バトンパスや加速のスピードなど圧巻の見せ場に観衆は沸き立ちます。二人が同時にテープを切り、他の選手も次々となだれ込みました。世界陸上の一景かと頂きましたが、実況時間は夜なので、〈秋高し〉の昼間の情景とは合致しません。ということは学校の運動会!スマホの動画にゴールを切る胸がくっきりと映っていて、動かぬ証拠となりました。(角野 京子)
風強き日には粕汁濃く料る 冨安トシ子
粕汁は絞りたての酒粕が手に入る初冬に度々作る家庭料理。中に入れる具も各々で違いそれぞれの家庭の味があるようです。作者は〈風強き日〉つまり寒くなった日には酒粕を多目に入れたと!!まったりと酷のある粕汁でさぞかし温まったことでしょう。ちなみに、下戸の私は粕汁でも顔が赤くなります。(藤田 壽穂)
改札にスマホをかざす文化の日 松山美眞子
新しい技術が社会のインフラになっていくのは時代の流れ。作者は今年九十五歳。新しいことにチャレンジする気持をいつも持っています。スマホも自由に使いこなす作者。当然、電車やバスの料金はスマホ決済です。季語が効いている一句。(三代川次郎)
冬めくや子犬の足に布の靴 進藤 正
かつての我が家、子どもたちが成長して妻と二人の暮しとなり「犬かわいがり」の日々でした。進藤さんも散歩中に布の靴を履いて歩く子犬に思わず立ち止まったのでしょう。子犬を見つめる優しい眼差が見えるようです。それと共に〈冬めく〉という季語によって、子犬が少しでも寒い思いをしないようにという飼主の愛情あふれる気持が察せられる、優しく楽しい一句になりました。
(三澤 福泉)

原稿募集 句会や誌上の作品から感じた楽しい俳句について
二百五十字程度で自由にお寄せ下さい