味噌汁に何でも入るる残暑かな 糟谷 倫子
連日の猛暑酷暑、風鈴や打水などの風流では凌げない暑さです。夏ばて気味の体のためには栄養をと思いますが食欲不振、料理をする気力も失せ…。しかし、掲句はそんな状況を打破する究極の一策。具を工夫すれば栄養価も上がり、目前が変われば食も進みます。日本食の一汁一菜は万能です。「こんなものを」といわれても大丈夫、「これは愛のあかし」といいましょう。〈何でも入るる〉は正に魔法の言葉、膝を打ちました。(小林伊久子)
掃苔や花咲く草は残しおく 西山 厚生
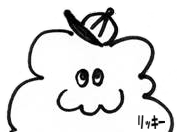
掃苔はまず元気のいい草を抜くことにはじまります。供花はすぐに枯れてしまいます。お墓でねむっておられる方に作者は花が咲いてる草、又はこれから可愛い花が咲く草だとわかり残しておくとおっしゃっています。なんて優しいそして心の余裕にも感心しました。時々参っておられるのでしょうか。私などはこの際と全部汗だで引っこ抜いて帰っております。(谷野由紀子)
まだ泳ぎゐるかの形に鮎焼けぬ 井村 啓子
鮎漁の解禁。早朝、川を泳いでいた鮎が昼には塩焼となって賞味されます。その姿は魚体をくねらせ尾鰭を跳ね上げて、まるで泳いでいた時のように焼き上げられています。掲句から東吉野の天好園で今年の鮎漁解禁日にいただいた美味しい鮎の塩焼を思い浮かべました。作者も化粧塩を付け泳いでいたかのような姿と淡白な美味の両方で、鮎の塩焼を堪能されたことでしょう。私までまた食べたくなってきました。(今村美智子)
開山祭を明日におろちが火を吐きぬ 福長 まり
大蛇踊りは全国に伝承されていますが、作者によると大山の山開きとのことでした。古事記や出雲神話に出てくる須佐之男命に退治された八岐大蛇ですね。確か、酔い潰れてしまったのが敗因だったような。お酒の失敗談の最たるものですね!作り物のおろちとはいえ、火を吐く大迫力に沸いたことでしょう。明日の山開きを前に意気軒昂な作者が目に浮かびます♪(岡田万壽美)
店先に蚊遣火燻るなんでも屋 中川 晴美
なんでも屋で親しまれている店は、町や村に必ず一軒はありました。箒、塵取などの掃除道具から笊、束子などの炊事道具が何列か棚に並んでいます。苺の苗やアイスキャンデーも売っていました。今も、法隆寺の門前や、石切さんの参道に健在で、結構、繁盛している様子です。店先の蚊遣火の匂が懐かしく、覗いて見たくなりました。(角野 京子)
熱帯魚眠らぬ街の喫茶店 志々見久美
喫茶店ではなくてスナックでしたが、若い頃、熱帯魚が泳ぐ水槽がカウンターに置いてある店によく行きました。店内は少し薄暗く、水槽にスポットライトが当たり、熱帯魚が涼しげに泳いでいました。なかなかムードのある店でした。水割りかカクテルを飲み、マスターとたわいない話をして店を出ました。この句からそんな若き日を思い出しました。(松井 春雄)
おにぎらず作る小五の夏休み 五味 和代
〈おにぎらず〉。調べてみますと平成二年、連載料理漫画『クッキングパパ』に登場したのが初出とか。ご飯を手で握らず、大判の海苔で風呂敷包みのように包むだけのおにぎりの一種とのこと。おにぎりとは違って手でぎゅっとは握らないため「おにぎらず」という名で広まったとのことです。小学五年生といえば、炊事などにも興味を抱く時期。楽しみながら炊事に親しめる〈おにぎらず〉でした。(中谷恵美子)
